C1〜C4の虫歯(う蝕)の進行と治療法をやさしく解説
虫歯は進行度によって C1〜C4 に分類されます。早期に見つけられるほど、治療の負担は小さく、歯を長く残しやすくなります。各段階の「状態・症状・治療の選択肢」を患者さん目線でまとめました。目次
C1:エナメル質に限局した初期の虫歯
状態:歯の表面(エナメル質)に白濁(ホワイトスポット)やごく浅い脱灰が見られる段階。穴がないことも多いです。
主な症状:自覚症状はほぼありません。見た目の変化に気づく程度。
診断のポイント:視診・触診、乾燥下での白濁確認、X線(必要に応じて)。
治療の選択肢:フッ化物応用とブラッシング・食生活の見直しで再石灰化を促し、経過観察。表面に小さな穴があれば最小限削ってレジン充填を行います。
ポイント:この段階で見つけられれば「削らない・削っても最小限」で済む可能性が高いです。
C2:象牙質まで進行した虫歯
状態:虫歯がエナメル質を越えて象牙質に到達。
主な症状:冷たいもの・甘いものがしみる、時々痛む。
診断のポイント:X線で進行範囲を確認。隣接面(歯と歯の間)に生じることも多いです。
治療の選択肢:虫歯を除去し、レジン充填またはインレー(詰め物:セラミック/金属)で修復。歯質の厚みや欠損範囲で材料を選びます。
ポイント:「早めの受診」で神経を残せる可能性が高まります。しみ始めたら放置しないことが大切です。
C3:神経(歯髄)まで進行した虫歯
状態:象牙質を越え、歯髄に炎症や感染が及ぶ段階。
主な症状:ズキズキ痛む、何もしていなくても痛い、夜間に悪化する、温かいもので痛む等。
治療の選択肢:根管治療(歯内療法)で感染した神経を取り除き、根の中を清掃・消毒・封鎖。その後、強度確保のためクラウン(被せ物)で覆います。
ポイント:痛みが落ち着いても感染が治ったとは限りません。自己判断で中断せず、最後の被せ物まで完了させることが再発予防につながります。
C4:根だけ残る末期の虫歯
状態:歯冠が大きく崩壊し、根(歯根)のみが残る、または根の先に病変がある状態。
主な症状:痛みが無い時期もありますが、膿がたまると腫れ・痛み・口臭の原因になります。
治療の選択肢:保存が難しい場合は抜歯。欠損はブリッジ・義歯・インプラントなどで補います。残存歯質や全身状態、清掃性などを踏まえて最適解を提案します。
ポイント:抜歯後の治療計画(仮歯期間、骨造成の必要性、最終補綴)まで含め、トータルで設計すると満足度が高まります。
C1〜C4の比較表(症状・治療・来院回数の目安)
| 分類 | 進行部位 | 主な症状 | 主な治療 | 来院回数の目安* |
|---|---|---|---|---|
| C1 | エナメル質 | 自覚症状ほぼなし | 再石灰化の管理/小さなレジン | 1回(経過観察は定期的) |
| C2 | 象牙質 | 冷・甘でしみる | レジン充填/インレー | 1〜2回 |
| C3 | 歯髄(神経)まで | 強い痛み・自発痛 | 根管治療+クラウン | 複数回(数回〜) |
| C4 | 歯根・根尖病変 | 痛みが無い時期も/腫れ | 抜歯+欠損補綴(ブリッジ等) | 計画により数週間〜数ヶ月 |
* 来院回数は目安です。虫歯の大きさ、清掃状態、全身状態、医院の治療方針で変わります。
予防とセルフケアのコツ
- フッ化物配合歯みがき剤を毎日使用(うがいは少なめの水で1回程度)。
- 毎日のフロス・歯間ブラシで隣接面う蝕を予防。
- 間食・糖の回数をコントロール(回数>量が虫歯リスクに影響)。
- 3〜6ヶ月ごとの定期検診で早期発見・早期対応。
しみる・痛む・詰め物が外れたときは要受診
我慢するとC2→C3へ進行しやすく、治療が大がかりになります。お早めにご相談ください。
▶ Web予約はこちら
よくある質問
Q. C1はどれくらいで治りますか?
A. 穴がない初期う蝕は、セルフケアの改善で進行停止が期待できます。数ヶ月単位で経過観察し、変化をチェックします。
Q. C2でセラミックとレジン、どちらが良い?
A. 欠損の大きさ、咬合力、清掃性、審美性、費用などで選択します。小さければレジンで十分なことも多いです。
Q. C3の根管治療は痛いですか?
A. 麻酔下で行うため多くは耐えられる範囲です。術後の違和感は数日残ることがありますが次第に落ち着きます。
Q. C4でも残す方法はありますか?
A. 条件が整えば外科的な処置(歯冠長延長術など)や根管治療で保存できるケースもありますが、割れ(縦破折)や歯質量が不十分な場合は抜歯が適切です。
※本記事は一般的な解説です。実際の診断・治療は口腔内の状態、全身状態、生活背景によって個別に判断されます。気になる症状がある方は受診してください。

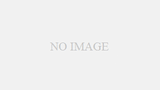
コメント